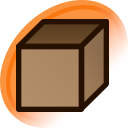Artist's commentary
ゆく年くる年
深々と雪が降り積もる。夜の静寂(しじま)に、鐘が鳴る。
暗い空をわずかに染める雪明かりと、家々に灯る明かりだけが、吐く息の白さを浮かび上がらせる。白くまだらな坂道をザクザクと踏みしめて歩く、帽子に着物姿の奇妙な三人組を、師走の街を急ぐ人びとは気にも止めない。まばらな夜景を背に石段を登り、やがて、紅い提灯を掲げた一軒の屋台の前で足を止めた。
「へいらっしゃいッ!…おや、今日は連れさんが?」
「はい、部下の唐瓜と茄子です。この年の瀬に残業に付き合わせてしまったので、その詫びに」
自分の背より低い暖簾を窮屈そうにくぐり、腰かけた上司の背の染め抜きの鬼灯紋を、二人の小鬼はそわそわと躊躇いがちに見ていた。
「どうしました?」
鬼灯は手でめくった暖簾越しに、不思議そうに声をかける。
「いっいえ!」
「今座りまーす!」
二人は急いで長椅子の左側に滑り込む。とたんに立ち上る湯気に包まれ、その暖かさにほっとした。コンロにかけられた鍋からは、美味しそうな匂いが漂う。
「…鬼灯様が連れてってくれるっていうから、なんかもっとこう、すごいとこ行くのかと思ったけど…」
「シーッ!失礼だろ…!」
ひそひそと顔を合わせる唐瓜と茄子の様子に、ねじり鉢巻の似合う店主は豪快に笑った。
「ガッハハ!変なのはお互いさまだろ?大晦日だろうが何だろうがラーメン一筋の頑固モンに、それを毎年大晦日に食いにくる地獄の鬼神様だもんなァ!」
え、と声をあげて唐瓜が隣を見ると、鬼灯は脱いだキャスケットを手に、鬼の角にかかった髪をかきあげているところだった。
「…何見てるんです?帽子被ったまま食べるんですか?」
そう言われて、慌てて帽子を脱ぐ。足元の小さな電気ストーブの温もりがありがたい。年月を経た趣あるカウンターの隅のワンセグでは、紅白歌合戦が佳境に入っていた。
「正直、長いものであれば蕎麦だろうがうどんだろうがラーメンだろうが、好きなもの食べればいいと思ってるんですよ。何にせよ、ここのラーメンはとても美味しいですから」
「かれこれ十五年くらいのお得意さんよォ。今日はいつもの感じで?」
「ええ、ラーメン大盛り三つに、それぞれ餃子と炒飯…あと、熱燗も三つつけてください」
「いっ、いやそんなに食べられませんって!ていうか、悪いですって!」
天下の閻魔大王第一補佐官に一介の部下が支払いさせるなんて恐れ多いと、唐瓜はブンブン両手を振った。
「食べられると思いますよ。書類整理は案外重労働ですから。それに、こういうときくらいしかお金を使う機会もないので。奢らせてください」
除夜の鐘がまたひとつ鳴る。湯がぐらぐら沸き立つ音、とんとんと刻むまな板の音、テレビから聴こえる流行りの歌。微かに響く電車の音。そのほかは、舞い散る雪に吸い込まれるように音が遠い。
「静かですね」
少し温くなった日本酒をちびりと飲んで、唐瓜が後ろの寂しげな夜景を見やる。
「俺、こういう景色嫌いじゃないよ。風情がある、っていうのかな」
ぽつりぽつりと会話を交わす部下たちを、鬼灯は手酌で熱燗を注ぎながら眺めていた。
唐瓜も茄子も、小鬼と言えど立派な大人で獄卒だ。しかも官房長官レベルの立場の自分を相手にしても、臆することなく仕事をこなしている。偉いひとが相手だからと尻込みしてしまう部下が多い中、程よい距離感のこの二人の存在は貴重だった。
「…今日は本当に、助かりました」
猪口を片手に、鬼灯は小さく頭を下げる。唐瓜がまた慌てて何か言おうとした時、カウンター越しに大きなどんぶり鉢が差し出された。
「へい、ラーメン三丁お待ち!」
ほかほかの湯気と醤油の香ばしさの中に、大きな焼豚が存在感を放つラーメンに、プリプリの大ぶりの海老が鮮やかな炒飯。にんにくの匂いが際立つ餃子も揃えば、遅い食事の準備は整った。
「いただきます」
三人声を揃えて手を合わせ、割り箸を手に取る。一口スープを含めば、旨味と塩分が寒空の空きっ腹に染み渡る心地がした。
「美味い!」
茄子が声をあげ、夢中で麺を啜る。鬼灯の手前遠慮がちだった唐瓜も、今はパラパラの炒飯に舌鼓を打っている。鬼灯は餃子を酢醤油にくぐらせ、熱い肉汁を感じながら頬張った。
「口に合いましたか」
「…美味いです。いや正直、思ってた以上に美味いっす。今まで食べたラーメンの中で一番美味いかも」
「うん。素朴って感じかな。みんなオーソドックスなやつなのに、全部丁寧に仕事してあって、余計なものがないっていうか」
見た目に反してあっさり仕上げられた肉厚の焼豚に、添えられたしゃきしゃきのもやしと薬味の刻みねぎ、よく染みた味玉、歯応えのいいメンマ。鶏ガラの旨味がきいたスープは細めのちぢれ麺によく絡む。
「あんた、お目が高いね。それがうちのこだわりでね。親父の味をずっと守ってんだ」
「いい仕事していますよ。お父さんの代から変わりません。ここは味噌ラーメンも美味しいんですよ。もっと雪が積もった極寒の日にバター増しにしてかっ込むのが最高なんです」
「いやぁ、そう言ってもらえると嬉しいねェ。よっしゃ、特製いなり寿司もサービスだ!」
満面の笑みの店主の傍ら、最後の除夜の鐘が鳴る。百八つの煩悩を取り去る静かな音色。紅白歌合戦はいつの間にか終わり、新年に向かう静かな祈りを映し出す。
百八つでは到底間に合わないほど、今の世は毎年混乱を極めている。いくら人間を呵責して送り出しても、罪を働く者は後を絶たない。変わらずこの店を訪れ、静かな街を眺め、この一杯を味わうときだけ、世界が何もかも変わらずにいられているような、そんな気がするのだ。
『あけましておめでとうございます!』
時報を境に、厳かな雰囲気はどこへやら。振り袖姿のアナウンサーが賑やかに中継している。鬼灯は居住まいを正して向き直った。
「あけましておめでとうございます、唐瓜さん、茄子さん。今年もよろしくお願いします」
「こ、こちらこそ、よろしくお願いします!」
「わーい鬼灯様と年越ししたー!」
「呑気だなぁお前…」
無邪気な二人を見て、鬼灯の表情が僅かに弛む。少し酔っただろうか。天変地異並みに移り変わる世の中で、何気ない会話ができるのが何故か嬉しい。獄卒たちが次々帰省していくなか一人残務に埋もれていた鬼灯を、この二人は帰省をやめて手伝ってくれた。自分はお礼に奢るくらいしか感謝を表す手段を知らないが、こうやって誰かと変わらない時間を過ごすこと。それが幸せなのかもしれない。
夜の静寂が、少しだけ賑わうなか、鬼灯は目を閉じて、心の中で呟く。
「良い年になりますように」
応えるように、どこかから柔らかな鈴の音が、聞こえた気がした。新玉(あらだま)の夜に、軽やかに雪は降り積もる。