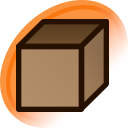Artist's commentary
阿求
Image Description
最初にその感覚を抱いたのは、とある天狗と縁記について会話していた時だった。
求聞持の力を持つ私には初めての感覚。既視感である。
正確に言えば、俗にいう既視感ではないのだろう。
一致する今と過去とを記憶が照合した後に、深い懐古の気持ちが自らの身を包む。
なんて心地がいい。
嗚呼、とため息が漏れ出しそうになる。
けれど、しかしこれは。
私の物ではない。
これは、きっと先代の……。それから、はて、珍しいこともあるものだ。と思った。
転生時に消失する記憶の内訳に、例外なく感情というものは含まれているものだと思っていたから。
事実、これまで御阿礼の子らが蓄積した知識を参照した時には、感情が伴ったことはなかった。“私”は縁記に関する事だけを代々引き継いでいるのだから、これは縁記にまつわる記憶と感情なのだろう。
よほど強い想いだったのか。
時期は消失してしまったのか、あの感情の持ち主が先代のどの“私”かはわからない。
私からしてみれば“私”であって私の物ではない感情。
訪れた既視感が過ぎ去ってみれば、我が身ながらおおよそは他人事なのである。
感情が心から乖離するのは、いささか後味が悪い。けれども、想いが強ければ、あるいは。
阿求としての私がこの世を離れても、何かの拍子で“私”が阿求であった頃の感情が
来世にも蘇る事があるのかもしれない。
それはとてもとても……。そんなことを考えてしまった。
夜目を効かせて歩く闇路に、小さいけれど、強い光が差した気がした。
頭の中で何かが外れる甘い音がした。
それからというもの。
困ったことにこの既視感が、縁記の編纂を行う際に度々打ち寄せるようになった。
正直、仕事にならない。今と過去を未来に記すのが縁記なのだから、過去の記憶を参照しないわけにはいかない。けれども過去の記憶や記載を参照するたびに当該“私”の感情が押し寄せる。
その度に筆が止まる。
だが、御阿礼の子として当代の縁記を書き上げねばならない。“私”たちが私を苛む。
書かなければ。書かなければならない。私も“私”たちと同じように。
あの闇路に、光を灯すべきではなかった。
歩いていくだけなら夜目で事足りた。
私が歩いてきた道を照らしてはならなかった。
道の先にあるものを見るべきではなかった。嗚呼。
“私”は書かなければならない。