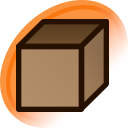Resized to 35% of original (view original)

Artist's commentary
誰も私のことを知らない、遠い遠い街で暮らしたいな
潮の香りとウミネコの声、寄せては返す波の音。港には数えきれないほどの船が停泊していて、そのほとんどは動き出す気配がない。もう役目を終えてしまったのか、それとも今日は日曜日だから休みなのだろうか。
「なんだ、つまんないの」
ため息をついて柵に肘をつく。別に船が盛んに出入りしていようと、それに飛び乗ってあてのない旅ができるわけではない。浪漫を求める海賊にも、豪華客船の乗員にもなれやしないのだ。ただ世間の荒波にもまれもせず、ぷかぷかと浮いているだけ。
流石に今更、何者かになれるとは思っちゃいない。二十数年生きて、自分の身の丈くらいは分かっている。なれないのは重々承知の上で、せめて誰かに必要とされる人生が良かった。今では港に停留する船や自由な鳥たちどころか、自動販売機にすら羨ましさを覚えてしまうのだ。岸から岸へと人を運ぶ、魚の死骸を喰らう、人々に潤いをもたらす。それぞれに役目がある。
港町は穏やかだ。まばらな観光客や広場ではしゃぐ子どもたちと同じように、方々から"要らない"という烙印を押された私にも潮風を運んでくれた。普段は恨めしく思ってしまう"必要な人たち"だってここではフェアだ、私と同じ。
「はぁ、帰りたくねー」
小さな叫びは雄大な海に届く前に、ウミネコの鳴き声がかき消した。誰にも届きやしないのだ。まぁ、所詮はこの鳥たちだって、ちゃぷちゃぷと揺蕩う船たちだって、どこへでも行けるというわけではない。私と一緒だ。
「だけど、せめて。誰も私のことを知らない、遠い遠い街で暮らしたいな」
何のしがらみもないどこかに錨を沈めて。もしかしたら、私を必要としてくれるかもしれない場所で。そう望んだところで、今日も家に帰るしかないのだ。