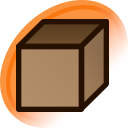Artist's commentary
妄想のままに書きなぐる
その日、小町は珍しく仕事を少しもサボらずにこなした。たまに真面目にやると、「やればできるのに何故いつもサボるのか」と、サボらなかったのに説教を喰らうのだから納得がいかない。しかし今日はその説教もなかった。無論褒められたわけでもない。小町がサボらなかったのは映姫の様子を伺う為だった。四季映姫には精神的に脆弱な部分がある。いつもは凛として真っ直ぐで、強い御方である。だが、「裁く」という重大な責務を担っているせいなのか理由は小町にもよくわからなかったが、十数年に一度、どうしようもなく弱ってしまうことがある。今日はその十数年に一度のときだと、小町は確信した。「四季様、仕事終わりましたよ」「あ…、はい」言われて気が付くなんて、今日は重傷かも…そう思いながら、やっと閻魔様の大仰な椅子から立ち上がった映姫の肩に、優しく手をかけた。「四季様。」静かに名を呼び、背中を撫ぜるように自分へ寄せようとすると、映姫は促されるままに小町の方へ体を傾けた。映姫の目から涙が一粒落ちる。映姫は隠すように顔に手を当てた。「堪えちゃだめですよ、四季様」堰を切ったように涙が溢れ、映姫は何も言わずに泣き出した。こういうとき、映姫は小町にすんなり自分を預けてしまう。小町はそれを当然のように受け入れるし、むしろ促すほどなのだが、後で映姫が強い自責の念を抱いてしまうことも知っていた。他者を裁く立場でありながら自分の弱い部分をまざまざと見せつけ甘えてしまうことは、相手が誰であっても許せないらしい。小町からすれば、(本当にくそ真面目で頭が固い。)しかしそれが四季映姫の性格であり、その上で、この石頭でひとには鋭く説教するくせに自分の脆さには無頓着でいきなりこんなに弱ってしまうような上司を愛して止まないのだ。だから、映姫が後で傷ついてしまうとしても手を離すことなどできない。その涙が、自分の前でしか零れないことも知っているから尚更である。ほんの少しの罪悪感に胸をちくりと刺されながら、抱きしめていた腕の力を緩めた。少しだけ顔を上げた映姫に小町は目を細めて笑んで見せ、いつもは説教ばかりなのに今は震えている唇を塞いでしまった。(この人を放っておくくらいなら、地獄に堕ちる方がマシだわ。) ■…という妄想。こまえーきは早く結婚するべき。