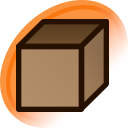Artist's commentary
内田眞悠理誕生祭2022
「いらっしゃい。あと少しで出来るから座っていてくれ」
乃子様に屋根裏の一室に通してもらうとトマトと玉ねぎの甘い香りが漂う。
「ごきげんよう。もしかしてラタトゥイユですか?」
手料理をご馳走したいという話だけ聞いていたけれど、彼女の好物や場所がここで調理器具の制約があることからもだいたい予想はついていた。
「ええ。自分が好きでよく作ると前に話しただろう?」
そう言いながら手際よく盛り付けていく。
手馴れた手つきからしても、実際、日常的に作っているのであろう。
先輩が料理をしているのだから本来なら手伝うべきなのだろうが、ここは彼女の宮殿なので余計な手出は無用だと判断して言われた通りに卓につく。
間も無くシンプルな皿に盛り付けられたラタトゥイユが2つ卓に並べられ、彼女も腰を下ろした。
スプーンを手に取る。そして──
「酸味は抑えてあるはずよ」
表情に出したつもりは無かったのだが、何を考えているか勘づかれたらしい。そう、自分は酸っぱいものが苦手なのだ。
先輩の手料理だ、恐る恐る食べるというのは失礼だ。
相手も自分の好みをわかっていてこう言っているのだから大丈夫。
そう思いながら口に運ぶ。
「美味しい……美味しいです!」
いざ食べてみたら、酸っぱいかどうかなんかよりもシンプルに美味しい、そう感じた。
「だろう?日羽梨なんかはもう少し酸味があるのを好むのだけれどね」
提供する相手によって味付けを変えられるぐらい作り慣れているということなのだろう。凝り性な彼女らしい。
曰く、しっかり煮込むことでトマトの酸味が和らぐのに加えて、南瓜の甘みも合わさって優しい味わいになるのだとか。
「レシピのメモを取っているぐらい凝っているのも納得の味ですわ」
部屋に入った時に持っていたメモ、あれは調理時のポイントなどを調理中に記していたのだろう。
凝り性の彼女のことだ、作り慣れていてもそういうところは欠かさないのだろう。
「ああ、これ? これはメモではなくて詩集」
「えっ」
「料理しながら読書するのはお行儀悪かったかしら?人の目を気にしなくていい空間だからつい」
とんだ勘違いをしてしまった。
煮込んでいる間に本を読むのが習慣になっているらしい。
本が汚れないように着けているカバーのせいで手帳のように見えたのだ。
「……冷めないうちに食べよう」
「そうですわね」
────
「それにしてもどうして手料理を」
一皿食べ終えて、鍋に残っていた分のおかわりを盛りつけながら疑問を口にする。
「さっきも言った通りだけど?」
「いえ、そうではなくて。お誕生日なのですから、普通あたくしが作る側ですよね?」
彼女は納得したような顔をしてから、何かを思い出したように少し笑った。
「この前ね、日羽梨が後輩に手料理を作ったという話をしてきたのよ」
後輩というのはあの子のことだろう。
「それを聞いて、羨ましくなってね」
「はぁ……」
「それで手料理を作ってあげたい後輩ってだれだろうって考えたら、浮かんできたのは君だったんだよ」
自分は今、何を聞かされたのだろうか。
いや、聞かされたのは何故彼女の誕生日なのに彼女が手料理を作ったのかという話のはずだがそういうことではなくて。
手料理を作ってあげたい後輩が、あたくしだった。
彼女はどういう意図をもってこの話をあたくしに?
思考が渦巻いていって──
「え、どうして泣いてるの?!美味しくなかったかしら?!」
「いやっ……違く…てっ」
「無理して食べなくていいから」
「無理してないですぁっ 美味しいですっ!」
整理のつかない考えを誤魔化すように、おかわりした分を口に運んでいく
「ちょ、じゃあなんで泣いてるの」
「うれ……うれしくて……」
「泣く程うれしいの?え、そんなに?」
「はいっ……」
あたくしに食べてほしいと作ってくれたラタトゥイユはとても美味しいので、それだけは間違って伝わってほしくない。
実際はうれしい以外の感情もあるのだけれど、彼女をこれ以上困惑させたくない。
気持ちの整理はしっかりついてないけど、それだけは確かだった。
──結局、ラタトゥイユの味付けは完璧で酸っぱくなかったけど、あたくしの涙のせいで少ししょっぱくなってしまった。