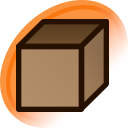This image is unavailable on Donmai. Go to Danbooru or disable safe mode to view (learn more).
Artist's commentary
「まんまとはめられた、わけですか」
ゆっくりと両手を上げながら、背後に立つ人物に話しかける。
資料室のみがかれたキャビネットに写りこんだ姿。女性。20歳前後。
カールスラント技術省の標準的な作業衣を着ているがこれは変装用だろう。右手にはー拳銃。
「そうね、あなたの賢さに助けられたわ」
下唇をかむ。姉から釘は刺されていたのだ。現役ウィッチにして、本国の技術士官。
そんな肩書きがあったところで、私に情報員の真似事など。
後悔しても遅い。いまは少しでも情報を得て、この場を切り抜ける手段を考えないと。
「ストライカーが無くとも、ウィッチを相手に拳銃など効きませんよ」
「”知っている”わ。私もかつては魔女だったのだから」
この人物は、正体を隠す気はないのだろうか。確かに拳銃の構えは素人のそれではない。
ただ、声に混じったわずかな震え。
私を振り向かせないのは、正体を知られることを恐れているわけではないのだ。
銃を突きつけた対象と向かい合う。そういう事が平然と出来るほど、荒事に
慣れた人物ではないらしい。
私が考え込む間より早く、背後の人物が口を開く。
「戦ってほしい相手がいるの。エーリカ・ハルトマン大尉。あなたのお姉さんにね」
ドクン、と心臓の音がのど元までせり上がってくる。今の動揺を、悟られただろうか。
互いに顔が見えないことに助けられたのは私かもしれない。
「姉は・・・私闘は行いません」
「それも「知っている」わ。長く本国にいたあなたより、お姉さんには詳しいかもね」
「私を人質にするつもりなら、そうしたところで姉は動きませんよ」
「・・・本当にそう思っているなら、お姉さんのこと”何も知らない”のね」
背後の人物が何かを床に投げ落とす。炭酸飲料の栓を開けるような、わずかな噴出音。
ついで、甘ったるい麻酔エーテルの香り。
「でも、そうね。保険のために手は打ってあるの。ゲルトルート・バルクホルン中佐。
最近は一線を引いて、妹さんとご一緒らしいわね」
エーテルで意識が薄らぎ、体の自由を失いつつ無ければ、今度こそ動揺を隠すことは出来なかっただろう。
最後の声を振り絞る
「なにも・・・しらない」
「何?」
(そう・・・この人は何も”知ってなんかいない”姉様が本気で怒ったらどうなるのか・・・知らないんだ・・・)